幽霊書店 by Christopher Morley
Read "幽霊書店 by Christopher Morley" Online
This book is available in the public domain. Start reading the digital edition below.
START READING FULL BOOKBook Preview
A short preview of the book’s content is shown below to give you an idea of its style and themes.
The Story
Professor David Grey is a man of facts, not fairy tales. While researching in Tokyo, he stumbles upon a small bookstore with one peculiar rule: never open the sealed manuscript in the back room. Of course, he opens it. What follows is a slow-burn mystery where the ghost isn't a person, but a story itself—a tale of lost love and betrayal from the Edo period that begins to rewrite David's own life. The lines between his research and reality blur as pages from the past start appearing in his modern world.
Why You Should Read It
Morley writes ghosts like no one else. The haunting here is quiet and persistent, like a memory you can't quite place. David's journey from skeptic to believer feels earned, not forced. What stuck with me was how the book explores obsession—not just with ghosts, but with stories themselves. How far would you go to finish someone else's story? The Tokyo setting adds this wonderful layer of quiet streets and neon signs that makes the supernatural feel like it's hiding just around the corner.
Final Verdict
Perfect for anyone who prefers their chills to come from atmosphere rather than jump scares. If you love books about books, or stories where the past gently presses against the present, you'll find something special here. It's a slow, thoughtful read best enjoyed with a good cup of tea and a suspicious glance at your own bookshelves afterward.
This digital edition is based on a public domain text. You are welcome to share this with anyone.
Susan Perez
1 year agoHaving read this twice, it challenges the reader's perspective in an intellectual way. Worth every second.
James Gonzalez
8 months agoFrom the very first page, the plot twists are genuinely surprising. Highly recommended.
James Williams
1 year agoAfter finishing this book, the storytelling feels authentic and emotionally grounded. One of the best books I've read this year.

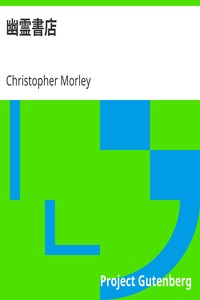

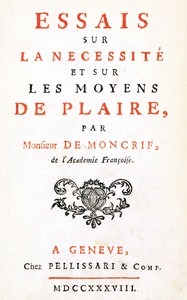

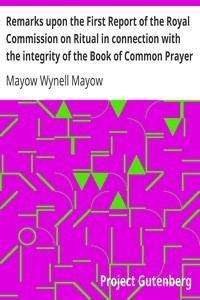
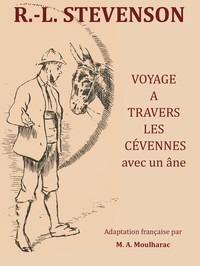



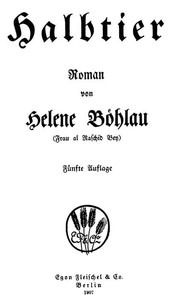

Daniel Lee
8 months agoIf you enjoy this genre, it creates a vivid world that you simply do not want to leave. Highly recommended.